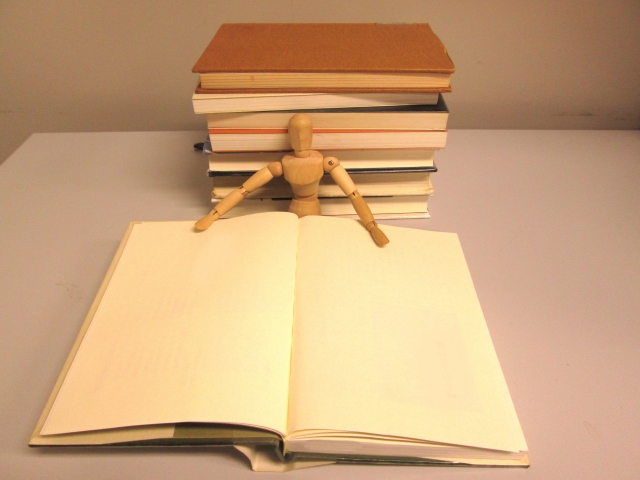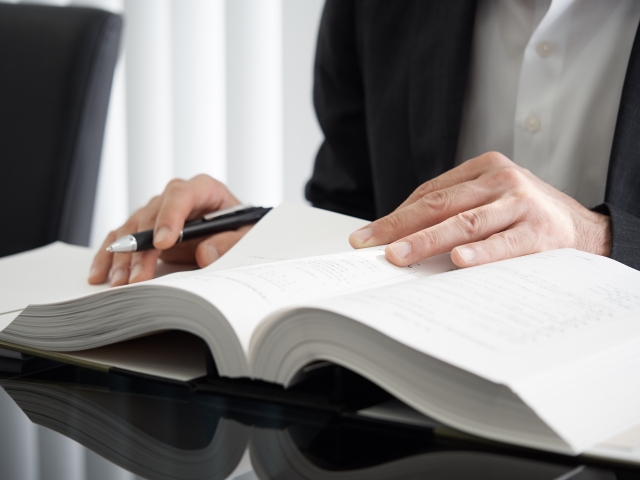税金のひとつに、「固定資産税」があります。
家屋にも固定資産税が掛かることは、ご存知の方も多いですよね。
ですが、どのように税率が計算されているのか、なぜ据え置かれる年と下がる年があるのかについては、よくわからないという方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、家屋の固定資産税についてお伝えします。
固定資産税とは
はじめに、「固定資産税」とは、どういうものなのか見ていきましょう。
固定資産税は、「家屋」や「土地」、「家屋や土地以外の有形償却資産」に掛かる税金のことです。
土地や家屋も、車と同じように税金が掛かり、毎年必ず納めなくてはなりません。
そして、この固定資産税という税金は、人によって支払う額に差があるのも特徴です。
それは、同じ市町村に住んでいる人であっても違います。
例えば、ある人は毎年10万円で、ある人は20万円、またある人は15万円などと違うのです。
それはなぜかと言うと、家屋や土地といった「固定の資産」では、市区町村が登記簿などで実態を調査して、その人の所有する家屋の評価額に応じた額を課税しているからです。
一方、有形償却資産はそれができないので、申告されたものに対して課税されます。
今回は、家屋の固定資産税についてお伝えしていくので、有形償却資産や土地については触れません。
しかし、課せられた税金をきちんと納めることは、国民の重要な義務となっています。
そして、固定資産税は、下がる年もあれば、据え置かれる年もあります。
ですがもし、固定資産税を払わなければ、各自治体によって、課税対象である家屋などを差し押さえられてしまいます。
きちんと、納めるようにしましょう。
家屋の固定資産税の計算方法や注意点とは
先ほど、固定資産税がどういうものなのかについて、ご説明しました。
この記事では、「家屋の固定資産税」についてお伝えしていきます。
ですが、家屋の固定資産税は、一体どのように計算されているのか、気になりますよね。
固定資産税の税率は、「再建築価格方式」で評価され、決定されています。
家屋の固定資産税の場合には、この方式で評価されて出た「家屋の評価額」が「課税標準評価額」になるのが普通です。
そのため、家屋の固定資産税が下がるかどうかは、この「評価額」がカギとなります。
支払う税額は、「課税標準評価額」×「税率」で計算されます。
そして、「課税標準評価額」は、日本全国で一律、1.4%となっています。
しかし、この「税率」については、各都道府県および各市町村が決めることができるため、地域によって差があります。
財政状況が困難な場合には、多少の引き上げもあるようです。
また、家屋の固定資産税は廃屋であっても、そこに建っていれば毎年税金が掛かるので、注意が必要です。
家屋の老朽化で税金が下がることはあっても、ゼロにはならず、家屋を取り壊さない限り、納税する必要があります。
家屋の固定資産税は実際どのくらい支払うの?
では、実際には、どのくらいの家屋に、どのくらいの固定資産税が課せられるのか見ていきましょう。
家屋の固定資産税には、大きく分けて、一般的な家屋と新築の2つの場合があり、それぞれ計算方法が異なります。
一般的な家屋では、先ほどお伝えした公式(「課税標準評価額」×「税率」)に当てはめて計算します。
仮に、家屋の課税標準評価額が、800万円として計算しましょう。
「800万」×「1.4%」なので、11万2千円が固定資産税として支払う金額になります。
一方、新築の場合の計算方法は、上記の公式では出しません。
2016年3月までに建てられた新築の家屋については、一定の期間、税額が半分に下がるという制度があります。
もちろん、どんな家屋でも該当するわけではありません。
・3階建てである
・耐火(あるいは準耐火)構造である
・床の面積については、50㎡~280㎡の場合に120㎡までが減額される
上記のような条件があります。
こうした条件を満たしていれば、課税標準評価額が同じ800万円であっても、以下の計算になります。
「800万」×「1.4%」÷2
支払う額は、5万6千円です。
ただし、この減額は、課税された年度から数えて「3年度分のみの減額」なので、それ以降は税金が上がることになります。
家屋の価値が下がれば固定資産税も少しずつ下がる?
よく「家屋の価値は、時間の経過によって下がる」という話を聞きます。
「ならば、家屋の固定資産税も少しずつ下がるのでは?」と誰でも考えますよね。
もちろん、基本的には下がっていくのですが、実際のケースでは、そうではないこともあるので注意が必要です。
なぜかと言うと、土地や家屋は、3年ごとに「評価替え」を行うからです。
評価替えというのは、評価額を新しく計算し直すことを指し、「再建築費評点数×経年減点補正率」で計算します。
この再建築費評点数とは、現在、同じ建物を建てた場合に、いくら掛かるかを表すものです。
経年減点補正率は、評価額を下げるために使うものです。
この計算式で出た額と、以前の評価額を比較し、低い方を新しい評価額として適用します。
そのため、新しい評価額が高い場合は、所有者の負担にならない低いほう(つまり、これまでの評価額)が据え置かれます。
これによって、家屋の見た目はだんだん古くなっていっているのに、固定資産税は下がらないということがあるのです。
とは言っても、その家屋が老朽化した場合は、再建築価格の20%まで下がります。
ちなみに、そこまで下がった後は、それが据え置かれ、さらに下がることはありません。
大体、木造の住宅なら20年、鉄筋コンクリートで造られた住宅なら60年ほどで、下限になるのが一般的です。
家屋の固定資産税は下がるのにゼロにならないのはなぜ?
はじめに、「家屋の固定資産税は下がっていくけれど、ゼロにはならない」とお伝えしました。
少しずつ下がるのであれば、いずれはゼロになりそうなものですが、そうならないのは、なぜなのでしょうか。
それは、家屋と行政サービスが一体だからです。
「家屋がある=家までの道(道路)があったり、家で使う水道(上下)なども整備されている」ものと考えます。
また、その家の子供が小中学校に通うといったこともありますが、それも行政サービスです。
考えてみればわかると思いますが、行政サービスを受ける以外にも、家屋は重要な役割を果たしています。
就職活動などにおいても、住所は必要です。
そのため、「不動産を持っている=行政のサービスを受けている」ことになり、家屋にも税金が掛かるのです。
また、税金の行方は、あまり気にしないことが多いものですが、固定資産税が何に使われているのかもお伝えしておきます。
固定資産税として支払われた税金は、主に、都市計画の実現などに使われます。
住んでいる地域の機能を維持し、未来の街をより良くするために必要な税金なのです。
そのため、家屋が古くなって税率が下がっても、20%で据え置きなのです。
工夫次第で家屋の固定資産税は下がる
先ほどお伝えしたように、家屋の固定資産税は、家屋が古くなれば、必ず下がるというものではありません。
ですが、やはり固定資産税は高いので、これから家屋を立てる人であれば、なるべく税金対策をしたいですよね。
ここでは、どうすれば家屋の固定資産税を下げることができるのかを、お伝えします。
先ほどもお伝えしたように、家屋の固定資産税は、「再建築費」で考えます。
そのため、建てるときに掛かった費用ではなく、この家屋を今再び建てるとしたら、いくら掛かるかというのが基準です。
ですから、その再建築費を安く抑えることが、家屋の固定資産税を抑えることに繋がります。
その再建築費を決める数値は、総務省が決めていますが、それを知れば対策法が見えてきます。
例えば、エアコンの場合、壁掛け式は、動かせるものなので課税されません。
ですが、ビルドイン式だと、固定されているため課税されます。
また、ソーラーパネルも、課税対象になるものとそうでないものに分かれます。
そのため、ソーラーパネルを設置する際には、課税されないものを選ぶことが重要です。
これから家屋を建てる人は、税金対策を上手に行ない、固定資産税が少しでも下がるようにしておくと良いでしょう。
固定資産税の仕組みを知って税金対策に役立てよう
今回は、家屋の固定資産税についてお伝えしましたが、いかがでしたか?
家屋の固定資産税の評価額は、3年ごとに見直されますが、必ず下がるわけではありません。
これから、家屋を建てようと思っている方は、固定資産税の掛かるものと、そうでないものをよく確認してから建てると良さそうですね。
また、今ある家屋は、軽減税率などの制度を活用してみると、固定資産税を下げることができるかもしれません。
参考にしてみてください。